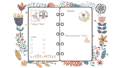第9話|削るように書く、伊豆大島のメモペン

竹芝桟橋から高速船に乗り、伊豆大島へ向かう。
東京を出て、海の上をまっすぐ進むだけで、空の色が少しずつ変わっていくのがわかる。
この旅は、ほんの少し重たい記憶を、どこかに残すためのものだった。
大島の港に着いた瞬間、風が変わった。
火山島特有の乾いた土のにおいと、潮の香りが混ざったような、どこか懐かしい空気。
宿に荷物を預け、外に出ると、赤い道が海に向かってまっすぐ伸びていた。乾いた土の匂いと潮の香りに包まれながら、私は自転車にまたがり、島の中心部へと進んだ。
その途中、黒い外壁の小さな店を見つけた。
「灰墨屋」とだけ書かれた木の看板が掲げられている。
目立つわけではないが、妙に存在感のある佇まいに惹かれて、自転車を止めた。
引き戸を開けると、店の中はひんやりと静かだった。
棚には墨のような色の紙やインク、メモパッドが並んでいる。
そのなかでひとつ、短くて太い、黒ずんだ軸の筆記具が目に留まった。
「それなぁ、火山灰でつくったメモペンなんですよ。」
奥から現れた店主が、低く穏やかな声でそう言った。
「削るように書くペン。インクにも細かい火山灰が混ざってて、書くたびに紙の上が少しずつ変わるんです。」
手渡されたペンを試してみると、筆先はやわらかいのに、紙をこするとほんのわずかにざらりと音がした。
黒灰色のインクは、書いた文字のふちがかすかに残る。まるで何かを「記録する」というより、「刻む」ようだった。
「メモってさ、忘れるために書くんじゃなくて、置いていくためにあるもんでしょ。」
その言葉が不思議と胸に響いた。
忘れたくない、でもずっと覚えているのも少し重たい——そんな記憶に、ちょうどいい形がある気がした。
そのメモペンと、灰色のメモパッド、それに専用のインクカートリッジをひと揃い購入した。
店を出ると、島の風がまた少し強くなっていた。
文具店とは逆方向にある地層大切断面の崖まで、自転車で向かう。
切り立った岩肌は、まるで何万年もの言葉が積み重なってできているように見えた。
その前で立ち止まり、メモパッドを取り出す。
火山灰インクのペンで、一言だけ書いた。
忘れないけれど、引きずらずに残しておく。
インクの線が、ほんの少しだけ紙の凹凸に沿って広がった。
それは、傷でもなく、絵でもなく、ただそこにあった言葉のかたち。
宿に戻ってペンを拭くと、手のひらにすこし黒い粉が残っていた。
それが、不思議とあたたかく感じられた。
書くことは、ときに削ることに近い。
けれど、削った先に残るものもまた、自分だけの輪郭なのかもしれない。
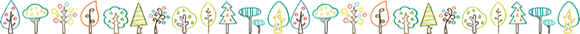
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]