第6話|ひかりの跡、甲府の蛍光ペン

甲府の夏は、東京よりもひときわ眩しい。
駅を出た瞬間、空の青さと日差しの強さに、目を細めてしまう。
けれどそのまぶしさが、今の私にはちょうどよかった。
なんとなく心がぼんやりしていたから、くっきりとした光の線がほしくなったのだ。
駅から少し歩いた先、小さな横丁の奥に、その店はあった。
白い暖簾に、筆文字で「光文堂」と書かれている。どこか懐かしいような、けれど初めて見るような名前だった。
引き戸を開けると、涼しい風とともに、紙の香りが漂ってくる。
棚には蛍光色のペンがずらりと並んでいたが、その中でも、淡い金色のラベルが貼られた1本に目を奪われた。
「それなぁ、ひかり寄せて書くペンずら。」
奥から現れたのは、麦わら帽子をかぶった年配の女性だった。
「ひかり寄せて書く…?」と聞き返すと、にっこり笑ってこう続けた。
「ようは、光集めてくれるインクってこった。日なたで書くと、あとからじんわり光るさ。
(つまりね、光を集める成分が入っていて、日なたで書くとあとからじんわり光るのよ)」
そう言って渡された紙に試し書きをしてみると、インクは最初ほとんど透明だった。
けれど、陽の当たる窓辺に置いて数秒後、文字がほのかに金色に輝きはじめた。まるで、夏の記憶が紙の上で目を覚ますようだった。
「夕方になると、色もまた変わってくんだよ。夏は移ろいやすいからなぁ。
(夕方になると色もまた変わるよ。夏は移ろいやすい季節だからね)」
その言葉が胸に残った。
今この瞬間の気持ちも、きっと変わっていく。でも、それでいい。変わっていくことそのものが、季節を生きることなのだと思えた。
私はその蛍光ペンと、光の反射が映えるという半透明の便箋を選んだ。
店主はペンを包みながら、「使うときは、天気のいい日にゃあ書いてみて」と言った。
(使うときは、天気のいい日に書いてみてね)
甲府の宿は、古い町家をリノベーションした一軒宿。
文具店とは少し離れていたけれど、甲府のまっすぐな道を歩くのが気持ちよかった。
夕方、縁側に腰をおろし、陽が残るうちに便箋を広げる。
金のインクでそっと書いた一行は、太陽が沈むにつれて、少しずつ淡い赤に変わっていった。
光は、記憶になる前に、いったん言葉になる。
そうして書いたその紙を、私はそっと光の差す窓辺に立てかけた。
明日の朝、どんな色になっているだろう。
甲府の夜はまだ暑かったが、風の中にどこか秋の輪郭が混じっていた。
けれど、夏はまだ続いている。
書き残したい光が、まだこの季節のどこかに確かにある。
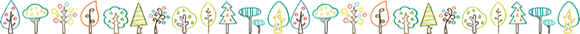
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





