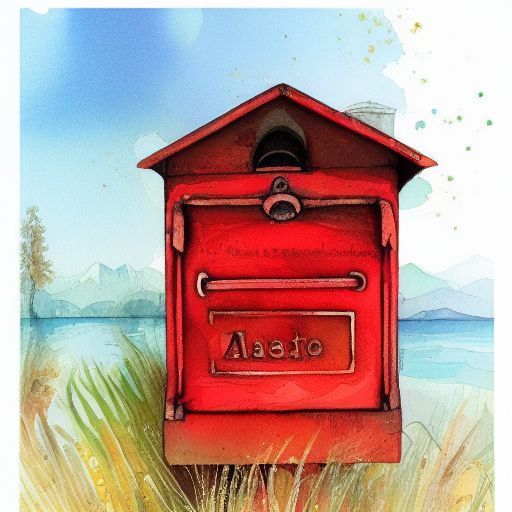第4話|潮風のことば、銚子のハガキペン
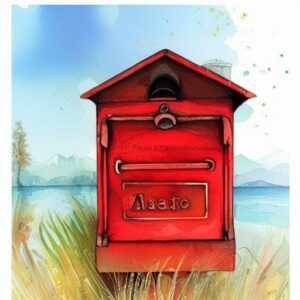
朝早く、東京駅のホームに立つと、ほんの少しだけ風が涼しかった。
それでも夏はしっかりと街に張りついていて、電車の窓を叩く光がまぶしく感じる。
今日は日帰りで、千葉の銚子へ向かう。海が見たくなったのと、もうひとつ。
「潮風をまとったペンがあるらしい」と、噂のようなメモをふと思い出したのだ。
房総半島の東端、銚子駅に着くと、潮のにおいが真っ先に鼻をくすぐった。
空は広く、少し白っぽくかすんでいて、遠くから汽笛のような音が聴こえた気がした。
歩いて向かったのは、漁港近くの旧商店街。人通りは少ないが、シャッターの下りた店の間に、ひとつだけ開いた扉があった。
看板には小さく「Sea Letter」と書かれていた。
ガラス戸の奥からは、潮風と紙の匂いがほんのり混じって漂ってくる。
中に入ると、店内はどこか懐かしい郵便局のような佇まいだった。
棚には手紙用品とともに、風化した瓶や貝殻のオブジェ、そして古い絵葉書が静かに並んでいた。
「潮風のハガキペン、お探しですか?」
声をかけてきたのは、麻のシャツを着た男性の店主だった。
「海辺の町に置いてある鉄のポストって、潮で少しずつ錆びるでしょう。
このペンも、そんな“時間のあと”をまとうように作ってあるんです。」
差し出されたペンは、細身で金属軸。ところどころにくすみがあり、それが逆に味になっていた。
キャップを外すと、ほんのり鉄と塩の混ざったような、潮風の香りがする。
「このインクは、時間が経つと文字の輪郭がにじみます。
でも、すぐに出すハガキには、むしろそれがいいと思っていて。」
試しに一枚、クラフト紙のハガキに宛名も書かず、短い言葉を記してみた。
夏の風に、間に合いますように。
文字は少しにじみ、紙に沈むように馴染んでいった。
まるで波打ち際のような柔らかさ。ぴたりと整った言葉より、今の気持ちをそのまま運んでくれる気がした。
ペンと数枚の専用ハガキを購入し、店をあとにする。
文具店と違い、投函所のような静けさが残る店だった。
その後、岬まで足を延ばした。
風が強く、帽子を押さえながら、防波堤に腰を下ろして、もう一枚ハガキを書く。
宛先はないけれど、言葉だけははっきりしていた。
書くことでしか、届けられないことがある。
近くの青いポストに、そのハガキをそっと入れた。
潮風の中、ハガキはどこへ行くのか。たぶん、どこへも行かない。
届け先のない言葉も、いつか、思いがけないかたちで自分に戻ってくるのかもしれない。
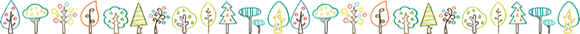
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]