第3話|湯気のことば、熱海の筆

「暑い日こそ、温泉に行きたいんですか?」
同僚にそう言われて、ちょっと笑ってしまった。けれど、そう。
冷房の風に頼りきった体が、どこか奥のほうでずっと冷えたままな気がしていた。
東京駅から新幹線でわずか50分。熱海へ向かう週末の旅を決めたのは、そんな小さな感覚のズレを直したくなったからだった。
駅を降りると、もわっとした湿気がまとわりつく。でも、それが心地いい。
海風に混じる温泉の硫黄のにおいも、どこか懐かしかった。
商店街を抜けて、坂をのぼる途中に、白い暖簾のかかった一軒の文具店を見つけた。
“Steam & Stroke”
ガラス戸の向こうから、涼しげな風鈴の音が響く。
「温泉と文房具?」という違和感が、逆に気になって、私は扉を開けた。
店内は静かで、ほんのりと温泉の蒸気を思わせるような湿った空気が漂っていた。
棚には筆や紙、そして湯呑のような形の小さな器が並んでいた。
そのひとつの横に、「湯気筆(Steam Brush)」という手書きのラベルが添えられていた。
「この筆は、インクではなく、蒸気で描くんです。」
奥から現れた店主がそう教えてくれた。
筆先に含ませるのは、ほんのりと香りのついた温泉の湯気を閉じ込めた特殊な液体。
それを使って書くと、書いた直後は何も見えない。でも、しばらくすると文字が紙の上ににじみ出てくるのだという。
「急いで読ませたい言葉には向きません。
でも、“ゆっくり届いてほしい気持ち”には、ちょうどいいんです。」
渡された専用の和紙に試してみると、筆が紙の上をすべる音だけが残った。
何も見えないまま、数十秒。ふわりと現れた線は、まるで湯気の形をなぞったような、淡く儚い文字だった。
私は、湯気筆と香り付きの専用液、和紙の便箋をひと揃い購入した。
「よければ、温泉で書いてみてください」と手渡された紙袋は、ほんのり檜の香りがしていた。
宿は、海の近くにある古い旅館。文具店とは坂の上と下で場所も離れていたけれど、それがよかった。
店を出てから宿に着くまでの時間が、心の中の“温度”をじんわり整えてくれた。
夜、露天風呂でしっかり体を温めてから、部屋で便箋を広げた。
窓の外からは、遠く波の音が聴こえていた。
筆先に蒸気液を含ませ、そっと一行。
いまはまだ、言えないこと。
しばらくして、紙の上に淡い文字がゆっくりと浮かび上がった。
伝えるのではなく、ただ滲ませるだけの言葉。
それもまた、書くということなのかもしれない。
帰り道、海を見下ろしながら思った。
この旅で少し、言葉との距離が変わった気がする。
急がず、焦らず、にじむまで待つ——そんな筆も、人生には必要なのかもしれない。
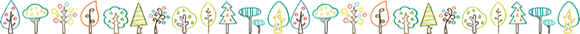
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





