第2話|呼吸をする鉛筆、奥多摩の森で

暑さが街にこもる夏の午後、私は東京駅から青梅線に乗り継ぎ、奥多摩を目指していた。
エアコンの効いたオフィスに居続ける日々が続く中で、ふと「深呼吸したくなるような空の広い場所に行きたい」と思った。
できれば、パソコンの前じゃなくて、空に向かって深呼吸できる場所へ。
列車を降りると、ひんやりとした山の空気が肌をなでた。都会の埃っぽさはどこへやら、空気の味がまるで違う。川のせせらぎが、どこからともなく聞こえてくる。地図も見ずに足の向くままに歩いていると、苔むした山道の入り口に、小さな木の看板がぽつんと立っていた。
“The Green Note”
白地に緑の文字。看板の下には「呼吸する文具、あります。」という一文が添えられていた。
木造の建物に入ると、ヒノキの香りと静けさが迎えてくれた。
棚には、紙ものや筆記具が並ぶ中、ひときわ目を引いたのは木箱に並べられた数本の鉛筆だった。
軸は淡い黄緑。光の加減で、ほんの少し葉のように見える。
「“呼吸する鉛筆”です。」
奥から現れた店主がそう教えてくれた。
「奥多摩の山桜の間伐材を使っていて、芯は少し柔らかめ。削るたびに、森の香りがほんのり立ちます。」
差し出された試し書き用の紙に、一本を手に取って書いてみた。
——するり。芯がやわらかく、紙にすっとなじむように文字が走る。
そして、確かに。削りたての鉛筆から、淡く木の香りが立ち上った。人工の香料ではない、山の記憶のような香り。
「この鉛筆は、文字を書くだけでなく、“考えごとをする時間”のための道具なんです。」
私は静かに頷き、3本の鉛筆と、手のひらサイズのメモ帳を購入した。表紙には押し葉のような模様があって、触れるとさらりと涼しい。
お店を出たあと、駅まで戻り、川の近くにある古民家を改装した一軒宿へ向かった。
文具店と宿は少し離れていたけれど、それがかえって、心の切り替えにちょうどよかった。
夜は窓を開けたまま眠りについた。川音と虫の声が、ひと晩中そばにいてくれた。
翌朝、鳥の声で目が覚めた私は、朝靄の中でメモ帳を開いた。
鉛筆を削る音が、静かな部屋に響く。
山の空気を吸い込んだ芯で書いた一行は、どこか音ではなく“呼吸”の跡のようだった。
書くことは、ときどき、息をすることに似ている。
そう思えた旅だった。
文字を埋めるために書くのではなく、ただ余白に自分を置いてみるような——そんな鉛筆との出会い。
帰りの電車、バッグの中からほんのりと木の香りがした。
しばらくは、呼吸のリズムで書いてみよう。
そう、思えた夏の奥多摩だった。
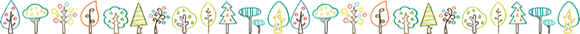
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





