第10話|書きかけの東京ノート

東京の夏は、まだ息づいている。
9月半ばだというのに、ビルの谷間には熱がこもり、秋の気配さえ感じられない。
旅から戻った日常の中で、私はふと、また文房具屋に立ち寄りたくなった。
場所は、神田の路地裏。
前に通りかかったときは気づかなかった、小さな木の扉。
表札のように控えめに掲げられている「紙灯舎」という店名は、どこか“誰かの暮らし”に入り込むような響きだった。
中に入ると、紙のこすれる音と、古い電灯のじりじりとした音が耳に残った。
棚には手帳やレターセットが整然と並んでいる。
その一角に、ふっくらと厚みのあるノートがあった。布張りの表紙。帯には「手紙のようなノート」と書かれていた。
「これは、誰かに宛てなくてもいい“手紙の余白”としてつくったノートなんです。」
そう教えてくれたのは、店主の青年だった。
「途中までしか書けなかった言葉とか、いまは出せない気持ちとか。
ぜんぶ“書きかけ”のままで、ここに置いておけたらって。」
ページをめくると、紙はわずかにクリーム色がかっていて、指にやさしく吸いつく。
しっかりと綴じられているのに、不思議と「完成させなくていい」と思わせてくれる空気をまとっていた。
私はそのノートを手に取り、そっと胸に抱えた。
書くことを急がなくていい場所。旅の余韻を、旅のまま閉じこめられるような場所。
そんなノートに出会えたのが、嬉しかった。
その夜、自室の机にノートを置き、やわらかな風の音を聴きながら、ゆっくりペンをとる。
でも言葉は、なかなか出てこなかった。
代わりに、ただ一行だけ書いた。
また書けるときが来たら、続きを。
それだけのページをそっと閉じた。
誰にも見せないつもりで書いたその一行が、自分にとっては何より確かな“再出発”の印だった。
翌朝、ノートの上には、まだ昨夜の熱が少し残っていた。
窓の外では、朝日が街を照らし、まだ抜けきらない夏の熱気がゆるやかに揺れていた。
すぐに書かなくてもいいノート。
書きかけのまま、そっと置いておくページ。
そんな余白があることが、きっと人生をすこしだけ優しくしてくれる。
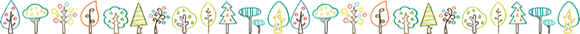
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





