第7話|香りをまとう、墨のサインペン

大阪から奈良へは、電車で小一時間。
週末の朝、いつものように文具を連れて、小さな旅に出る。
次の目的地に奈良を選んだのは、「香りのするペン」という不思議な言葉に惹かれたからだった。
春の奈良は、どこか時間がゆっくりと流れている。
奈良公園の鹿たちは相変わらず自由で、私たちのことなんてどこ吹く風。古い町並みに足を運ぶと、ふとした風に、線香のような、乾いた木のような、なつかしい香りが混ざっていた。
駅前の賑わいから少し外れた小路に、小さな文具と香の店があった。
古い町家を改装したその店には、障子越しの光がゆるやかに差し込み、床にはほんのりと墨の香りが漂っていた。
「どうぞ、香りの文具、見ていってくださいね。」
店主の女性は、和服にエプロン姿。店内には、筆や和紙、線香、そして…サインペン?
一見、和の世界と不釣り合いに見えたそのペンは、よく見ると、黒くて艶のある軸に、ほんの小さく「香墨(こうぼく)」という刻印があった。
「墨の香りがほのかにするサインペンです。揮発性のインクじゃなくて、墨をベースにしていて。」
試しに一本を手に取り、紙の上に文字を走らせる。
するすると滑るような書き味の後、ふわりと香りが立った。
墨のようで、でも少し甘さを感じるような、深くて落ち着いた匂い。
不思議と、書いた文字が「音」ではなく、「気配」になるような感覚があった。
それは、誰かに伝えるための言葉ではなく、自分の中でそっと沈めておくための言葉のようだった。
「墨って、書いてすぐには香りが広がらないんです。
じんわりと、あとから広がるでしょう? 心も、そうだと思っていて。」
店主の言葉に、私は小さくうなずいた。
今まで、言葉にすることばかりに夢中になっていた。何かを“表す”ためのペンばかりを集めていたのかもしれない。
けれどこのサインペンは、むしろ“言葉にならないもの”をそっと包んでくれるようだった。
購入したペンは、桐箱に入れてもらった。
箱を開けたときに、ふわりと香りが立つようになっているという。
箱の中には小さな言葉も添えられていた。
ことばは、香りのようにのこるもの。
帰りの電車の中、私はノートを開き、あえて何も書かずに、ペンのキャップをそっと外してみた。
しばらくして、紙の上に香りがふわりと染みこむような感覚があった。
書かなくても、伝わることがある。
旅をしてきて、少しだけ、そんな余白を受け入れられるようになってきた気がする。 静かな奈良の風は、春の終わりをやさしく告げていた。
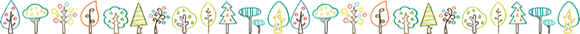
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]




