第5話|記憶を削る、レトロな鉛筆削り

伊丹空港のロビーで、ふと「旅慣れてきたな」と思った。
搭乗ゲートの先には、長崎行きの便。今回は飛行機だ。飛び立つ時間が、旅の輪郭を少しだけ強調してくれる。
いつもより少し高い空から、窓の外を眺めていた。白い雲、海、そして島々。春の光はまぶしくて、ふと小学生の頃に読んでいた、絵本の1ページを思い出した。鉛筆で描かれた、素朴な風景。あれは、どこか長崎のような町だった気がする。
長崎空港に降り立った私は、市内へ向かうバスの中で、かすかに胸がざわつくのを感じていた。
理由はわからない。ただ、今日はなぜか“懐かしいもの”に出会えそうな気がしていた。
坂道を歩き、古い町並みが残るエリアを抜けた先、小さな骨董と雑貨の店がぽつんとあった。木製の引き戸。小さな看板に、手書きで「文と記憶」と書かれている。
なんとなく、その文字にひかれて扉を開けた。
中は、時間が止まったような空間。
昔のインク瓶、万年筆の軸だけ、古い広告ポスター。そして、ショーケースの中に、ひときわ目を引く文具があった。
ゼンマイ式の鉛筆削り。
小さな黒いボディに、銀のクランク。少しかすれたロゴが、なんとも味わい深い。
「それ、1950年代のドイツ製なんです。」
声をかけてきたのは、店主らしき年配の男性。
「当時のまま、動きますよ。手でまわす感じが、なんとも言えんのです。」
私は、試してみてもいいかと聞いた。店主はにっこりうなずき、一本の鉛筆を差し出してくれた。
カリカリ、カリカリ。
機械の音が、店の中に小さく響く。鉛筆が回るたび、あの頃の教室の匂いが、ふっと鼻先をよぎった。静かだけど、確かに存在感のあるその音は、まるで記憶を削り出すようだった。
削り終えた鉛筆の先は、細く、美しかった。
書き味ではなく、“削るという所作”そのものに、私は不思議な満足感を覚えた。
「今は便利な道具がたくさんありますけどね、こういう時間を大切にする人が、最近また増えてるんですよ。」
私はその鉛筆削りを購入し、包んでもらうあいだ、ひとつ思い出した。
子どものころ、書くことが好きだった理由。それは“きれいな芯”があると、書き始めるのが楽しくなったからだ。
文具は、ただ道具じゃない。
記憶を呼び覚まし、今の自分をそっと照らしてくれる、そんな役目もあるのだと思った。
宿に戻ると、私は机の上に、例のデニムのペンケースと鉛筆削りを並べた。
旅先で拾い集めた時間たちが、静かに並んでいる。それを見ているだけで、心が少し整っていくのを感じた。
夜の長崎は、港の明かりがきらきらと揺れていた。
私は削ったばかりの鉛筆で、便箋に数行だけ、ことばを書いた。
「カリカリと 音にまぎれて 思い出す あのときの やわらかい心」
この旅には、まだ見ぬ言葉たちが、きっとたくさん待っている。
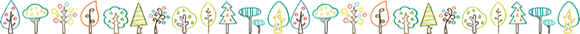
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





