第3話|金箔の光、言葉の重み

敦賀駅で乗り換えて北陸新幹線で金沢に向かう道中、窓の外をぼんやりと眺めながら、前日に京都で出会った竹の筆ペンの感触を思い出していた。
言葉は、ただ書くものじゃない。ときには、静かに手のひらに包むものなのかもしれない。
そんな気づきが、胸の奥にまだやわらかく残っていた。
金沢に着くと、冷たい風が少しだけ強かった。春はまだ浅い。けれど街並みはどこかあたたかく、石畳と古い家々がしっとりとした空気をまとっていた。
私は、ひがし茶屋街を抜けて、金箔工芸の工房兼ショップにたどり着いた。観光案内にも載っている、少し名の知れた店。だけどその奥に、ひっそりと筆記具だけを扱う一角があると、旅好きな友人が教えてくれていた。
格子戸をくぐると、そこにはまるで小さな美術館のように、丁寧に並べられた万年筆たちがいた。黒漆、銀蒔絵、朱のライン。どれも美しかったけれど、その中で私の目を引いたのは、金箔が一筋だけ貼られた漆黒の万年筆だった。
飾りすぎず、語りすぎず、それでもそこに“物語”が確かにある。まるで、秘めた強さをまとった言葉のような静かな存在感だった。
「よく見つけられましたね。その一本、うちでも特別なモデルなんです。」
奥から現れた店主は、金箔職人でもあるという女性だった。
「筆記具に箔を貼るのは、すごく繊細な作業で。ほんの一息で金がゆがむ。でもそれが、味になるんです。」
万年筆を手に取ってみると、思っていたよりも重かった。けれど、それは心地よい重みだった。書く前から、「今から何か大切なことを書くのだ」と背筋が伸びるような、そんな気持ちになる。
「実はその金箔、貼る位置をわざと少しずらしているんです。“完璧じゃない”からこそ、使う人の物語が乗るんです。」
彼女の言葉が、静かに胸に響いた。
私はこれまで、自分にどこかで“完璧さ”を求めていたのかもしれない。ちゃんとした道、ちゃんとした未来、ちゃんとした自分。けれど、旅に出てから、ほんの少しだけ、その“ちゃんと”がほどけてきていた。
「この万年筆で書きたい言葉、もう決まってますか?」
「……まだです。でも、たぶん、見つけにいく途中です。」
そう答えながら、私はその万年筆を手に入れた。
この旅が終わるころ、どんな言葉がこのペンの中にたまっているだろうか——そんなことを、ふと思った。
店を出ると、細い小道の先に、小さな桜の木が見えた。まだつぼみはかたいけれど、枝の先にほんのりと紅が差していた。 このペンには、まだ何も書かれていない。けれど、それがいい。
これからの旅で、ゆっくり、ゆっくり、言葉を紡いでいこう。
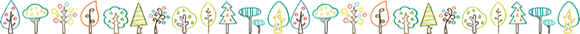
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





