第2話|静けさの筆、祇園の路地で

京都駅に着いたのは、午後の早い時間だった。
大阪から電車でほんの30分ほど。けれど街の空気は、がらりと変わった。背筋がすっと伸びるような、静けさと気配。季節は同じ春のはずなのに、ここには時間の流れ方そのものが違うように感じた。
私は祇園の細い路地を歩いていた。石畳がこつこつと靴音を返し、木造の町家が並ぶその通りには、観光地としての賑わいの裏に、どこか「昔」が残っていた。
目的もなく歩くのが、今回の旅のスタイル。けれど、なぜか今日は、手の中のガラスペンが静かにうながすような気がした。「あの店に行ってみなよ」と。
路地の奥、格子戸の前に「文」とだけ染め抜かれた暖簾が揺れていた。気づくとそこに吸い寄せられるように足を踏み入れていた。
そこは、小さな筆記具専門店だった。店内には墨の香りがほのかに漂い、竹や紙、木の素材が静かに並んでいた。主張しない美しさ。声高に「買って」と言わない文房具たちが、まるで呼吸をしているようだった。
「春の筆をお探しですか?」
現れたのは、着物姿の女性店主。やさしい声の奥に、凛とした強さが宿る。私はそっと小さくうなずいた。
棚の上に並べられた中から、彼女が一つ手渡してくれたのは、竹軸の筆ペンだった。表面はなめらかに磨かれており、手になじむあたたかさがあった。色は抹茶のような深緑。飾り気のない一本なのに、妙に落ち着く。
「竹は、春の息吹を一番早く吸い上げる素材なんです。しなやかで、でも折れにくい。」
試し書きをしてみると、インクがするりと筆から滑り出て、紙の上を泳ぐように走った。ガラスペンとはまた違う、流れるような書き心地。文字を書くというより、「気持ちが動く跡を残す」という表現のほうが近かった。
「日々の中に、“余白”を持てる道具です。」
その言葉に、私は心のどこかが軽くなるのを感じた。
ここ最近、言葉を“使う”ことにばかり気を取られていたように思う。でも本当は、言葉に“耳をすます”ことのほうが、ずっと大切だったのかもしれない。
筆ペンを包んでもらっている間、私は店の奥に貼られていた短い詩に目を奪われた。
「竹の筆 心をなぞれば 春も書ける」
名もない短詩。それでも、心にそっと染みこんできた。
店を出ると、祇園の空はやわらかい薄曇り。
桜の花びらがひとひら、筆ペンの包みに落ちた。私はそれをそっと取って、日記帳に挟む。
ガラスペンと竹の筆。今、私の旅かばんには、二本の道具がいる。
どちらも静かで、語りすぎないけれど、確かに寄り添ってくれている。
旅はまだ、始まったばかりだ。
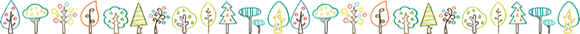
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





