第5話|景色のあと、佐渡の万年筆

夜明け前の東京駅。
始発の新幹線に揺られ、新潟港からフェリーで佐渡へ渡る一泊二日の旅。
この夏は、まだ終わらない。けれどその途中に、小さな風景をひとつ残しておきたくなった。
両津港に着くと、風がほんの少しだけ海の匂いを連れてきた。
港前のレンタサイクルで、自転車を借りる。マップは見ずに、ただ風の向くほうへとペダルを踏んだ。
入り江のゆるやかな坂を越えた先、ぽつんと現れた木造の平屋。
看板には「蒼筆」と、筆文字で彫られていた。海の青とよく似た、静かなたたずまいだった。
引き戸を開けると、紙とインクのやわらかな香り。
棚に並ぶ万年筆の中、ひとつだけ深い群青の軸が目を引いた。
小さな札には「風景記録筆」とだけ記されている。
「それなぁ、景色ん記憶が染みる万年筆だっけ。」
そう話しかけてくれたのは、麦茶を手にした年配の男性店主。
「書いたときの空気やら匂いやら、まるごとインクが覚えてくれるんさ。」
試しにメモ紙へと一行書く。
風を感じる心地よさ。
数秒後、インクの端がほんのり色を変えた。最初は藍色だったのに、陽に当たるとわずかに琥珀色が混じってくる。
「それが、ここで書いた証拠ってこったのさ。」
私はその万年筆と、専用インク、小さな旅ノートを選んだ。
店主はそれらを和紙で包みながら、ぽつりと言った。
「夕暮れに書くと、また違って見えるんよ。暑さで文字がやわらぐんさ。」
(夕暮れに書くとまた違って見える。暑さが文字にやわらかさを加えるんだ)
宿は、海を見下ろす高台にある古民家風の民宿。文具店とは反対方向だったけれど、それがちょうどよかった。
自転車を返してからチェックインし、夕食後に縁側でノートを広げた。
波の音と虫の声をBGMに、万年筆をそっと走らせる。
書くたびに、空気の手ざわりや風の粒が、文字の奥に沈んでいくようだった。
景色は撮れなくても、書いた手の記憶がそれを思い出させてくれる。
翌朝、フェリーを待つ港のベンチで、最後のページに言葉を残す。
書くことは、景色をそのまま写し取ることじゃない。
自分の目を、あの場所へもう一度誘うための印だ。
昨日書いたページをめくると、インクの色が少しだけ深く変わっていた。
それが、佐渡という時間に触れてきた証のようで、なんだか嬉しかった。
夏はまだ終わらない。
けれどこの万年筆は、今日の景色をそっと胸にしまってくれた気がした。
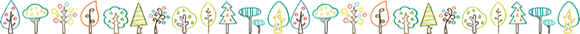
この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。
[文具探しの一人旅TOPページ]
[ニコブング TOPページへ]





